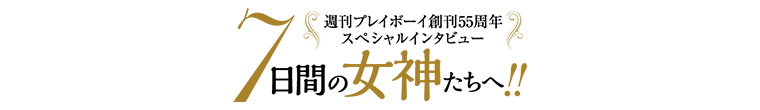『グラビアの読みかたーWPBカメラマンインタビューズー』笠井爾示 編 第二話「思い出を知る」 暗室作業にハマり、始めた“写真日記”
2022年9月9日 取材・文/とり

あまり表に出ることのないカメラマンに焦点を当て、そのルーツ、印象的な仕事、熱き想いを徹底追究していく本コラム。“カメラマン側から見た視点”が語られることで、グラビアの新たな魅力に迫る。週プレに縁の深い人物が月一ゲストとして登場し、全4回にわたってお送りする。
第13回目のゲストは、週プレで、初水着グラビアから井桁弘恵を撮り下ろし(デジタル写真集『いげちゃん』など)、CYBERJAPAN DANCERS写真集『BONJOUR!!』などを手掛けた笠井爾示氏が登場。『月刊シリーズ』の思い出のほか、自身の作品集やグラビアに対する素直な気持ちを語ってもらった。
――10歳から18歳までをドイツで過ごされ、高校卒業後に急遽、日本へ帰国されて。
笠井 最初のうちは全く日本に馴染めませんでしたよ。というのもドイツでは、街中を歩いているときにパッと目が合うと、知らない人でも挨拶をするんですよね。フレンドリーで表情豊かなドイツ人に比べると、日本人は何を考えているか分からないというか。人が怖くて、一時は電車に乗るのも億劫になってしまったほどでした。今の感覚では、それが普通なんですけどね。
――日本人は内向的な方が多いですしね。パーソナルスペースの感覚は、明らかに違うと思います。
笠井 その頃、内向的だったのはむしろ僕の方です。精神状態の悪い母親との接し方も分からなければ、気心知れた友達も近くにいない。そんななかで受験勉強もしていたので、知らず知らずのうちに相当なストレスを溜め込んでしまっていました。前回もお話しした通り、結果的に多摩美術大学に合格して通うことになるのですが、あまりのストレスで胃に負担をかけすぎてしまい、合格発表から1〜2週間が経った頃に倒れてしまって。「このままだと命が危ない」と、胃の3分の1と十二指腸の摘出手術をした関係で、大学には3ヶ月遅れて入学することになったんですよね。
――そ、そうだったんですね……。
笠井 僕が入学した多摩美のデザイン科には、グラフィックデザイン科と環境デザイン科の二つの分野があったんですが、3ヶ月も出遅れてしまったがために、希望していたグラフィックデザイン科には「もう席がない」と言われてしまって。「どちらの科に進もうと、1年のうちは大して授業内容が変わらないから。一旦、環境デザイン科に進んでみて、2年になったタイミングでまた考えてみるのはどう?」と勧められるがまま、環境デザイン科に入ることになりました。まぁ僕自身、ザックリと絵の勉強がしたかっただけで「絶対にグラフィックデザイン科じゃなきゃダメだ!」ってわけでもなかったので、すんなり受け入れましたけど。
――環境デザインというと、地域開発や建築にまつわる分野ですよね?絵の勉強とは、また違う気がするのですが。
笠井 そうです。だから僕以外は、みんな建築家を目指す学生ばかりでしたよ。思い描いていた分野ではなかったものの、せっかく入ったのなら、それなりに建築の世界に馴染んでみようと。まずはお小遣い稼ぎも兼ねて、建築事務所でのアルバイトから始めました。何も考えずに始めたアルバイトではありましたが、僕が働かせてもらっていた事務所は、磯崎新さんや伊東豊雄さんなど、日本の建築界の巨匠たちの模型を扱っているところで。下請けとはいえ、なかなか貴重な体験になりましたよ。
――それにしても順応力がスゴいですよね。10歳でドイツに移住されたときもそうでしたが、思うようにいかない場合でも与えられた環境にちゃんと馴染もうとされるのは、なかなかできることじゃない気がします。
笠井 いやいや。何なら僕の人生はずっとそんな感じですよ(笑)。案外、自分で決断した部分が少ないんです。ひとつあるとしたら、大学1年の秋頃にあった集中講座で暗室実習を選んだことですかね。取り立てて何か動機があったわけではないんですけど、いろんな実習があるなかでいちばん面白そうだと感じて。文字通り、暗室に入って写真をプリントする実習を1〜2週間ほど集中して受けていた時期がありました。……と、ようやく写真の話になりましたね(笑)。
――あはは。本当ですね。ということは、それが写真に興味を持つ最初のきっかけだったんでしょうか?
笠井 そうですね。暗室実習では、最初に実習用のフィルムと印画紙を渡されるんですよ。自ら暗室実習を選んだとはいえ、実物の印画紙を見たのはそのときが初めてでした。校舎で友達の写真なんかを撮って、暗室で8×10 (エイトバイテン)のサイズにプリントして。それが思いのほか面白かったんです。言ってしまえば、写真を撮る行為以上に、暗室で写真をプリントする作業にハマったんですよね。
――なるほど。確かに、真っ黒なフィルムから像が浮かび上がってくる瞬間はワクワクしそうですね。デジタルが主流の今は、なかなかできない体験です。
笠井 「一回の実習で終わるのはもったいないなぁ」と。大学内にある暗室は申請さえすればいつでも使用できたので、時間を見つけては暗室にこもって作業をしていました。今思うと、ひとりで黙々とできる没入感が良かったんでしょうね。大学に入って少しずつ友達が増えたとはいえ、まだまだ内向的な人間だったし、周りの同級生たちとの感覚の違いに、劣等感を抱いていたのも事実ですから。暗室にいる時間が、ある意味、癒しになっていたんだと思います。
――写真自体への興味はなかったんでしょうか?
笠井 「写真で何かを表現したい」みたいな発想は全くなかったです。それでも、暗室作業のために写真は必要だったし、“写真日記”という体(てい)で、毎日撮り溜めてはいましたよ。
――“写真日記”?
笠井 表現にしてしまうと、写真を撮る行為が一気に難しくなる。でも“日記”なら、日課として淡々と写真を撮っていられる。とにかく暗室で作業がしたかった僕にとって、“日記”は、好都合なお題だったんです。片や、学科で勉強していた環境デザインや建築事務所のアルバイトでは、「この建物には何故コレが必要で、この部分は何故こういう形をしているのか」と理屈で埋めていく作業が必要になってきます。プレゼンテーションとして「カッコいいから」では通用しない。それはそれで面白かったんですけど、“日記”の体(てい)で写真を撮り続ける行為は、そういった理屈から解放される瞬間にもなっていましたね。
――無理やり理由を探さなくても、単純に「日記だから」で日々を撮っていけると。
笠井 そうそう。そうやって写真を撮り続けていくなかで、ふと「写真家にはどんな人がいるんだろう?」と興味が広がって。アルバイト先の建築事務所が近いこともあり、アート作品を多数取り揃えていたパルコブックセンター吉祥寺店(現在は閉店)に写真集を見に行ってみたんです。そしたら、写真集のコーナーだけでスゴい面積が使われていて。なかでも、荒木経惟(アラーキー)さんの写真集がダントツで多かったんですよね。そこで初めてちゃんと荒木さんの写真集を見たとき、雷に打たれるような衝撃を受けました。日付入りの写真が時系列に並べられている写真集『平成元年』など、荒木さんが撮っていた写真も“日記”だったんです。
――ほ、本当ですね……!荒木さんといえば、妻・陽子さんとの生活の様子など、私小説ならぬ私写真をたくさん作品にまとめてこられた写真家。暗室作業のために笠井さんが始めた“写真日記”と非常に近い感覚で写真活動をされていた方だ、と言っても過言ではないですよね。
笠井 おこがましい話ですけどね。「コレ(日記)が表現になるのか」と、驚きしかなかったです。しかも、有名なタレントさんが写っていたり、女性の裸を写した写真のあとに、天皇陛下が映っているテレビ画面の写真が続いたりと、どれも荒木さんにしか撮れない“写真日記”だったんです。写真家をほとんど知らなかった当時の僕でさえも、ひと目でスゴい人なんだと理解しましたよ。そのような私写真集のとなりには、有名な女優さんの写真集も置いてあったし。そんな荒木さんに影響を受けて、僕も積極的に女性を撮ってみようかと、写真を撮る行為そのものにも興味が湧いてきたんですよね。
笠井爾示 編・第三話は9/16(金)公開予定! 「『月刊 井川遥』を見て思ったんです。『僕がやりたいのはコレだ』って」。思い入れのある『月刊』シリーズを語る。
笠井爾示プロフィール
かさい・ちかし ●写真家。1970年生まれ、東京都出身。
趣味=自炊
1996年に初の個展『Tokyo Dance』を開催し、1997年に新潮社より同タイトルの写真集を発売。以降、音楽誌、カルチャー誌、ファッション誌、CDジャケットなど、幅広いジャンルを手掛けるほか、『月刊 加護亜依』『月刊 神楽坂恵』『月刊NEO 水崎綾女』など、月刊シリーズでも活躍。
主な作品集は、『東京の恋人』、『七菜乃と湖』、『トーキョーダイアリー』、『羊水にみる光』、『Stuttgart』、川上奈々美『となりの川上さん』、階戸瑠李『BUTTER』など。CYBERJAPAN DANCERS『BONJOUR!!』、渡辺万美『BAMBI』、Da‐iCE『+REVERSi』、橋本マナミ『接写』などのタレント写真集や、頓知気さきな『CONCEPT』、武田玲奈『Rubeus』など複数の写真家による合同写真集にも参加している。